病気になって精神的に辛くなる原因ストレスを徹底解説!闘病・持病はすごいストレス
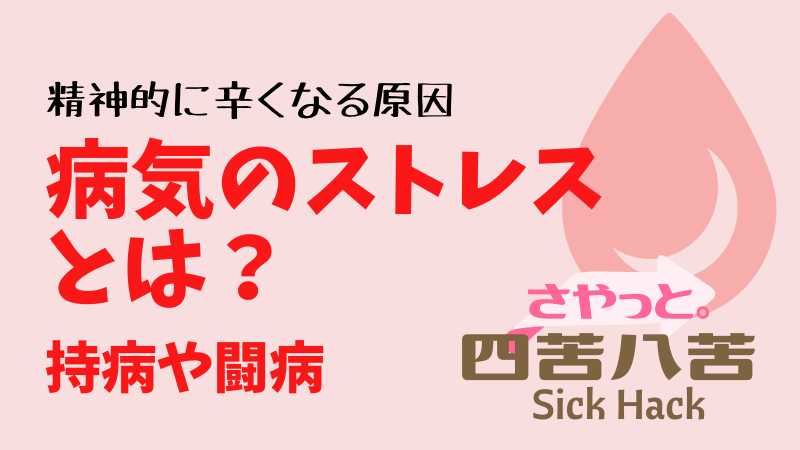
病気になると大きなストレスがかかる。
当たり前のことですが、このことにもっと注目するべきだと思うんです。
病気になると病気の症状のことにばかり目が向きがちですが、本人は精神的な辛さとも闘っています。
周囲の人が理解するためにも、本人が自覚するためにも、病気になると生じるストレスや精神的な負担をまとめました。
※病気によるストレスは多いので長いです。
遺伝性&進行性の難病持ち。そして精神保健福祉士。
17歳ごろから病状が悪化し始めたストレスで盛大に精神やられた経験あり。
メンタル弱いので病気のことではかなり苦労した。
今ではかなり上手にストレスマネジメントできています。
病気になって精神的に辛い人。
病気の人を支えていて、どんなことが辛いのか、どんなストレスがあるのかを知りたい人。
ただ大変だ辛いと感じるよりも、客観的に理解できた方がストレス対策に繋がる!
大体どんな疾病でも当てはまるようなことをピックアップしていますが、生活に大きな影響を及ぼすような病気向け
症状によって慢性的に大きなストレスを受け続ける
痛み、不快感、苦痛、違和感、だるさ、不自由さ……
これらのすべては精神的な部分に常に攻撃を受け続けているのと同じ。
一時的なら我慢できても、長期的にさらされると人が変わるほどのストレスです。
痛みや苦痛は他のストレス反応を引き起こす
痛みなんて我慢する!ちょっとくらい辛くても頑張る!って本人が思っていたとしても、 身体は自分の状況に対してストレス反応を起こします。
ストレス反応は多すぎて説明するとキリがないけど、気が立ってイライラすること、頭痛や腹痛、落ち着きのなさや集中力のなさ、不眠など、 人の生き様に直に影響することばかり。
ストレスが慢性化すると、うつ状態や無気力、解離(離人症や解離性健忘など)、身体の不調にまで繋がって、もう踏んだり蹴ったりです。
常に拷問を受け続けていたらどうなるか?を考えてみると理解しやすいかもしれません。
特に変化の後は辛い。慣れるまでが大変
看病をする人や、八つ当たりされる周囲の人にわかってほしいのは、慣れるまでは大げさに反応しても許してあげてっていうこと。
同じ痛み、同じ症状でも最初に起こったときや状態が悪化した直後は、状態の落差が大きいほど精神的なダメージが大きくなります。
生まれてからずっと貧乏な人と、億万長者から転落した人とでは感覚が違いますよね。
少しでも症状が悪化したとき、変化したときは精神的にショックを受けるので、実際の症状によるストレスよりも大きなストレスがかかります。
ショックによるストレスは和らいでいくので、今は辛いけどそのうち慣れるって知っておくのが大事です。
思い通りにならないことのストレス
電車が遅れたり、商品の袋が開けづらかったり、風邪を引いたりしてイライラした経験は誰でもあるはず。
病気になると、そんな思い通りにいかないことのてんこもり。
スマホがフリーズするだけでもイライラするのに、それが自分の身体だったら物凄いストレスですよね。
通常の楽しみやストレス解消法を失ってしまう
病気によって今まで楽しみとしていたことや、ストレス解消のためにしていたことが出来なくなることも、病気によるストレスを大きくしてしまう要因です。
身体を動かすだけでも精神的な安定を保つ効果がありますし、食事や入浴、歌うことや友人と遊ぶこと、趣味の活動など、本人が自覚していなくてもストレス解消の役割をしている活動がたくさんあります。
様々なことができなくなると、普段よりも大きなストレスがあるのに普段通りのストレス解消すらできなくなってしまう過酷な状況なんです。
精神的なエネルギーのタンクに穴が開いている状態
精神的なエネルギーというのが、気持ちの余裕や安心感、満足感や幸福感などを生むものだとしましょう。
病気になったときは、そのタンクに穴が開いてエネルギーがどんどん減っていってしまっているような状態。
憂鬱に悲観的になったり、八つ当たりをしてしまったり、不安になりやすくなったりするのは全く正常な反応です。
精神が攻撃を受けているんだ!ということを忘れないで、ストレスと向き合いましょう。
周囲の人も 「病気のストレスに対する反応だ」と思って受け止めてあげてくださいね。
納得できない、コントロール出来ない感覚でエラーを起こす
自分のしたことによって起きたり、防げたはずだったり、責める対象がはっきりしていたりする問題と違って、 病気はランダムに降りかかりコントロール出来ないことがほとんどです。
理由と結果がわからない!攻撃を受けている感覚
病気になったときの辛さは、無実の罪で投獄されているようなもの。
誤認逮捕と違って、責める対象すらいません。
何が起こったのかわからない、何が悪いのかわからないストレスは相当なもの。
なんとか答えを見つけようとして間違った思考に陥って余計に辛くなってしまうことも。
自分が悪いのではないか?という疑問
物事が上手くいかなかったときや、人とトラブルが起きたときなど、何か悪いことが起こったときは誰しも自分に非がなかったかどうかは考えるはず。
病気の原因が体質的なものだったとしても、偶然だったとしても、 自分が何か悪いことをしてこんなことになったのではないか?という疑問はなかなか拭えるものではありません。
よほどの悪い生活習慣があって直接的に関連している場合であれば当然の思考かもしれませんが、そうでない人ほど自分を責めて辛くなってしまいがち。
何も悪いことをしていないのに、病気になったことに対してなんとなく罪悪感を抱いている人も少なくないと思います。
納得できないということのストレス
「怒っていたけど理由を聞いたら許せた」「悲しかったけど仕方がないことだと思えた」「不安だったけど対策をしたら安心できた」
理由と結果がわかれば、自分のなかで気持ちの整理ができることで楽になれることもあるし、何らかの対処をすることで落ち着くことができることは多いです。
ただ襲い掛かってくる病気というのは、どうしてもそういったストレスの解決法は使えません。
病気になった原因を探ることや、治す方法をなんとか見つけようとすることに無駄なエネルギーやお金を費やしてしまうことも。
得体のしれないものへの恐怖
幽霊、感染症、暗闇……人は得体のしれないものほど恐怖を感じる生き物です。
自分の身体や生活を脅かしているのに、その正体が見えない、何が起きているのかよくわからないというのは相当なストレスになります。
できる限り理解するための勉強や医師の説明は大切ですよね。
よくわからないものに苦しめられることで、救いを求めて宗教やスピリチュアルの世界にハマりやすくなる人もいます。
自分自身の存在にたいする嫌悪感
これは経験した人にしかわからないかもしれませんが、自分の存在自体が何か間違っていて欠陥のあるものなんだという感覚を抱くことがあります。
悪いことをしたからではなく、誰かにやられたわけでもなく、環境が悪いわけでもないとなると…… という思考が着地地点を間違えてしまいます。
そもそもこんなことが起こる自分自身ってなんなんだろう?
罪がないのに罰せられているような気分になり、ようするに存在自体が罪なのかと思ってしまう。
産まれてきたことを呪うことも。
ときに親を責めてしまうこともありますが、原因がわからないことに原因を見出そうとした脳のエラーです。
受動的になり、自己効力感が低下する
今までは自分で自分の人生をコントロールしてきた、選んできたという人も、病気になるとその感覚を失ってしまいます。
病気になる過程は自分の行動の結果ではないことがほとんど。
さらに病気になってからの闘いも、自分の行動の結果では思うようにいかないことも多いです。
物事にたいして行動して変えていく能力、自分次第で物事は変わっていくという感覚が壊れてしまいます。
避けられない損失で無力感を覚え、反発する力がなくなる
必死で努力して入った会社を病気になって働けなくなったら?
今までの生活がすべて壊れてしまって、すっかり違う人生を生きなければならなくなったら?
今まで積み上げてきたものがすべて無駄になる経験というのはそれだけでも辛いものですが、 病気によって「またいつ突然なるかわからない」という感覚を植えつけられてしまうことも。
「自分が何をしたとしてもまたすべて無駄になるかも」と思うと、物事に対して自分から変えていこうという気力を失ってしまっても無理はないです。
どんな行動でも、なんらかの目的があって、それが上手くいくという見込みを元に行動するものです。
病気によって襲い掛かる症状や問題に対して何もすることができないと、 自己効力感(自分が行動をしたらうまくいくという見込み)が根本的に低下して、あらゆることに対して気力を失ってしまうこともあります。
どんなに気持ちでは頑張ろうと思っても、脳が「どうせ無駄だし」とボイコットを起こす無気力状態になってしまうのです。
変えられないと思い込み、不安で臆病になる
自分の行動によって変えられないことが重なると、そもそも何かを変えようという姿勢自体を失ってしまうことも。
自分では何もできないと思い込んで周囲の人や何かに救いを求めるだけの子どものようになってしまいます。
「患者」である自分でしかなくなってしまうような状況も関わっているかもしれません。
特に若いときに病気になり、他の活動や社会的な関わりが少ない場合では、自分では何もできなくなる危険性が高いです。
「自分でどうにかしなきゃいけない」「人に助けてもらってばかりで申し訳ない」という気持ちはあり、何もできない自分に対する罪悪感だけは人一倍持っている場合が多いです。
どうしても不安がわき出てきて、挑戦しても上手くいかないことが怖くて、何もできなくなってしまいます。
変えられないことがあまりにも多すぎるために、実は自分で変えられることに気付いてもいないというのが一番多いケースかもしれません。
数少ないコントロール出来る部分にこだわる
病気によって思うようにいかないことが増えると、自分の思い通りにできることに対する比重が巨大化します。
部屋の環境や食事やスケジュールなど、自分の身の回りのことに強いこだわりを見せる。
取り組んでいることに関して、凄い情熱を注ぎこんで無理も通そうとする。
数少ない楽しみに依存して、邪魔されることが許せない。
周囲の人に思い通りに動いてほしくてわがままを言ったり、心配や親切心を利用してコントロールしようとしたりする。
これらのこだわりによって、病気だからってワガママ言うな!!病気なんだから大人しくしてろ!!と言われてしまうこともあるかもしれません。
理不尽だったり非合理的だったりして理解されづらいことでも、自分の精神的なバランスを保つために必要なことなんです。
「病気で可哀そうだから許される」とワガママを言っているわけではなく、病気によって失われた部分を補おうとしているということ。
人は一定量の我慢しかできないし、一定量の自由が必要なんです。
当たり前の生活や状態が奪われてしまったからこそ、「それくらいは守りたい」気持ちでしている行動に「それくらい我慢しろ」というのは酷かもしれません。
周囲の人がストレスを感じないような本人の自由を確保することで、問題にならないよう工夫しましょう。
自分の価値や生きがいがわからなくなって自己肯定感が下がる
病気になるといろんなことが出来なくなり、様々な役割を失い、苦しさや辛さばかりを感じることによって「自己」の姿も変わってしまいます。
存在価値を感じるために必要なものの欠如
病気になって社会や組織のなかでの居場所や役割を失うと、人として誰もが持っている「自分はここにいていい」「求められている」という感覚を持てなくなってしまいます。
仕事や家事ができなくなることによって、誰かのために何かをすることや貢献する機会が減ります。
特別認められていた、褒められていたということがなくても、誰でもなんとなく社会のなかで自分の存在価値は感じているもの。
それがなくなると、自己評価も低下しがち。
生きる価値すらわからなくなってしまう人もいます。
助けてもらうこと、支えてもらうことへの葛藤
病気になったら医師を始め様々な人の助けを借りることになります。
今まで当たり前のように自分でしていたこともできなくなり、人に頼ることに対して申し訳なさや情けなさを感じる人もいます。
特に、家族や親しい人に負担があり「迷惑をかけている」と感じて自分を責めてしまうときは辛いものです。
仕事や生活上で何かできないことがあったり、配慮してもらう必要があったりして、ちょっと人にお願いすることが増える状況でも、そういった葛藤に日々悩まされる人もいます。
頼ることが苦手な人や自立心が強い人では、精神的な苦痛が大きいでしょう。
頼りたくないのに頼らざるをえない状況にいら立ったり、人の助けは必要ないと強がったりして、むしろ感謝せずにひどい態度を取ってしまうこともよくあります。
色々してもらえることに感謝と嬉しさを感じる人もいますが、助けられる側の本人が一番辛い思いをしていることも多いのです。
自分らしさ自体を作り直すことになる
好きなことややりたいことをできなくなってしまったり、生きがいにしていた仕事や活動ができなくなったりすると、「これが自分だ」と思っていた自分のことがわからなくなってしまいます。
あなたはどんな人ですか?と訊かれたら、仕事や趣味について答える人が多いのではないでしょうか。
自分らしさを失って、病気の自分と向き合いながら新しくアイデンティティを作り直す必要があるのは大変なことです。
病気の影響で家族や友人との付き合い方まで変わってしまう場合では、親しい人から見た自分の姿すら変わってしまい、心の拠り所がなくなってしまうこともあります。
「お仕事は何をされているんですか?」「〇〇はお好きですか?」「お料理はしますか?」というような簡単な質問に対しても、病気によって出来なくなったことや変わってしまったことが邪魔をします。
「何をきかれても答えられない」というストレスに悩む人はとても多いです。
自分を責めやすくなり、幸せの方向性を失う
自己評価が下がることによって「自分は大切な存在である」という根本的な自己肯定感が下がってしまったらどうなるでしょうか。
自分を責めることが多くなり、自分のために何かをすること、自分自身が幸せになることに意欲を向けなくなっていきます。
申し訳ない気持ちや、なんとか人に認められたい気持ちばかりで行動するように。
自分が幸せになることを忘れ、なんとかして病気による損失を埋めようとする生き方に変わってしまうことも。
治って幸せな生活をしたいと思っていたはずなのに、 気が付けば何とかして「普通に戻らなければならない」というような強迫観念を持つようになって苦しむ人はとても多いです。
病気になって何があったとしても、価値があって幸せに生きる存在であることを忘れず、自分らしい生き方を見つけられるようにできると良いですね。
わかり合えない疎外感・孤独感
病気とは自分のなかで起こっていることなので、自分自身にしか理解できず、一人で闘う部分が多くなります。
通常の生活から自分一人だけ切り離され、周囲の人とは違う道を歩んでいるような感覚がすることも。
孤独感や疎外感は、病気になったときのもっとも一般的なストレスだと言えるかもしれません。
理解されないことが増え、共感できることが減る
風邪や花粉症なら誰でも「ああ、それね」と理解し合え、「辛いよね」と共感しあうことができます。
誰もがなるわけではないような病気になると、周囲の人と同じ感覚で話し合えることは少ないでしょう。
患者会などで同じ病気の人との関わりが推奨されているのも、孤独感を軽減するためです。
自分にとっては実際に起きている身近なことなのに、人にはまったく理解されずに誤解されてしまうこともあります。
病気によっては、偏見や誤解を受けやすく、悪意を受けることすらあるでしょう。
そんな孤独感と理解してもらえない疎外感のなかで、理解してくれる人に対して依存的になったり、逆に理解してくれない人に対して反発心を持つことは多いです。
わかって欲しいのにわかってもらえない辛さから、「どうせわからないくせにわかったようなことを言うな!」という怒りが湧くこともよくあります。
なかには、わかり合えないことで人との関わりを減らしてしまう人もいます。
気を遣って本心が言えなくなる
病気の話は楽しい話題ではないですし、暗い空気になってしまうこともある話題です。
話したいことがあっても、病気のことを話題に出すと悪いからと言えなくなってしまうことはよくあります。
また、今までは対等な立場でどんなことでも話していた相手でも、自分の病気を気遣って何かしてくれたり、優しく接してくれたりすることで関係性が変わってしまうことも。
相手に何か助けてもらっていたり配慮をしてもらっていたりすると、引け目から思うように振舞えなくなり、自分らしく人と関わることが出来なくなってしまいます。
なかには、病気だというだけで「助けよう」と過度に世話を焼こうとしたり、「可哀そう」と同情ばかり向けてきたりする人もいます。
「そうじゃないんだよなぁ」と思ったとしても、相手は善意でいるので本心が言えないもどかしさもあるかもしれません。
なにより、大切な人に心配をかけたくなくて自分の辛さについて話せなくなるのが、一番の問題です。
わかり合えなくても、ちょっと辛くなってしまうような話題でも、当たり前のように話すことができるような場ができるといいですね。
やり場のない不満を抱えている
長期的な重大な病気でも、一時的な軽い病気でも共通するのは、ストレスを抱えていても何も責めることができず、やり場のない不満を抱えることです。
気持ちの折り合いをつけ、なんとかストレスと向き合い、自分自身のなかで解決していかなければなりません。
その過程で人に当たってしまうことや、過度なストレスによって潰れてしまうことはあるでしょう。
そんなとき、病気によって大きなストレスがかかっていることを客観的に知っておくだけでも、気持ちの整理に役立つのではないでしょうか。
ストレスはどんな病気にもある症状です。
致命的な症状にまで発展しないよう、ストレスもケアしていきましょう。
この記事で挙げたことの他にも病気が原因のストレスがあるよ!という方はコメント欄にて教えていただけたら嬉しいです。
記事下方、関連記事の下にコメント欄があるので、よろしくお願いします!
